※この記事は三井農林株式会社からのPR依頼(イベント招待)を受けています。
こんにちは、ティーアドバイザーのMii(みぃ)@mii_teaparty です!
実は先日、大変ありがたいことに「プレミアムティーショップ nittoh.1909」の開催するイベント『和紅茶づくり体験 2024年春 -和紅茶を知って、つくって、味わう-』にご招待いただき、参加してきました!
今回はそのレポートとして、和紅茶の製茶工程を紹介しながら、イベントに参加した際の感想を記述していきます。
また、記事の後半では、三井農林株式会社の開発者担当者へのインタビューも掲載!
和紅茶作りへの熱い想いを語っていただきました!(Mii初の、紅茶業界人へのインタビューです!)
「どうにかしてこのイベントやnittoh.1909、和紅茶の魅力を伝えたい!」といろいろ詰め込んだ結果、このブログ始まって以来のボリューミーな記事になってしまいましたが、読み応えのある内容になっていると思いますので、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
このイベントレポートを通じてより多くの方が、和紅茶や、nittoh.1909というブランドに興味を持ってくれたら嬉しいです♪
YouTubeでも紹介しているので、こちらの動画もご覧ください!
「Miiのお茶会チャンネル」では毎週金曜日に、紅茶に関する動画をアップしています。
気になる紅茶の情報をたくさんお届けしているので、ぜひチャンネル登録してください♪
nittoh.1909 とは?
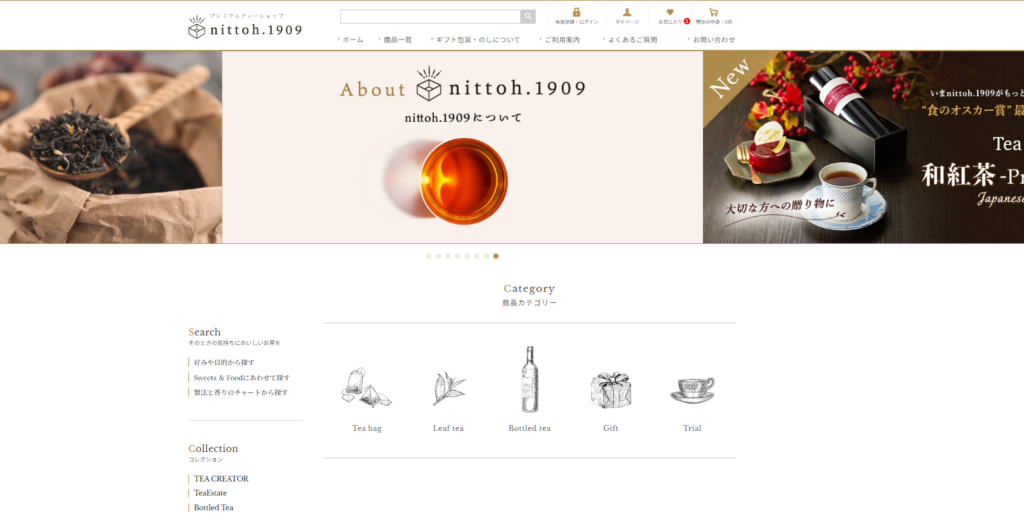
「nittoh.1909」は2021年4月に立ち上がった、謂わば日東紅茶のプレミアムラインです。
商品は、茶園や季節毎の個性を味わう「TeaEstate」、作り手の個性を味わう「TEA CREATOR」、独自の抽出製法で香りを味わう「Cold Brew Tea」等、お茶本来の味わいや美味しさを追求したこだわりのラインナップを取り揃えています。
またECサイトでは製品情報提供にとどまらず、お茶にまつわる文化の発信を行なっており、お茶についての知識や、作り手へのインタビュー、茶器に至るまでコラムが掲載されています。
オリジナル商品やコンテンツの開発の他、他業種、他企業とのコラボレーション、イベントの開催なども行っており、まさに「お茶を通して、つなぐ・かなえる・満たされるための場」として誕生したブランドです。
>> nittoh.1909 ECサイトはこちら
>> nittoh.1909 公式インスタグラムはこちら
イベント概要

| イベント名 | 『和紅茶づくり体験 2024年春 -和紅茶を知って、つくって、味わう-』 |
| 日時 | 2024年5月11日(土)10:00-16:00 |
| 会場 | 丸子紅茶(静岡県静岡市) |
| 参加費 | 6,000円(税込)※現地集合・現地解散、交通費自己負担 |
イベントでは、手揉みで和紅茶を作る体験のほか、和紅茶発祥とされている丸子地区で生産を行っている「丸子紅茶」の工場見学ができたり、自分たちで製茶したお茶のテイスティングもできちゃいます。
同様の和紅茶づくり体験イベントは2023年秋にも開催されていたのですが(詳しくはnittoh.1909のこちらのコラムをチェック)、好評だったこともあり今回その第2回が開催されました。
参加者は20人前後でしたが、参加者同士はもちろん、スタッフの方々とも和気藹々とお話しながらの楽しい体験イベントとなりました!
丸子紅茶とは?

会場は、国産紅茶発祥の地と呼ばれる丸子地区で生産を行っている「丸子紅茶」です。
丸子紅茶の村松二六さんは、国産の紅茶品種「紅富貴(べにふうき)」の栽培を日本で初めて成功させた第一人者でもあります。
丸子紅茶のべにふうきは、輝く紅色、ホットでもアイスでも香りが楽しめるまろやかな深い味で、ベルギー王室の御用達の品にもなっています。
和紅茶好きはぜひ一度、ご賞味ください♪
製茶の工程

ここでは大まかな紅茶の製茶工程を紹介しながら、イベントの感想を綴っていきます。
摘採

生葉(なまは)の若くて柔らかい部分である一芯二葉、三葉を摘み採ります。
(※摘採は製茶体験イベントの実施項目に含まれません。)
今回使用した茶葉は、日本で初めての紅茶・半発酵茶兼用品種である「べにふうき」のファーストフラッシュです。
萎凋

萎凋とは、生葉の水分を飛ばすことで、葉を萎(しお)れさせ柔らかくし、次の工程で茶葉をもみやすくするための作業です。
写真の左右にある大きな箱(萎凋槽)には青いネットが張ってあり、その下には機械から送り込まれた温風が吹いています。
この工程で10〜15時間ほどかけて、葉の水分を40-50%ほど減少させます。

この萎凋を行なっている倉庫の中は、摘みたてのお茶の香りでいっぱい!
ふとした瞬間に、青々とした茶葉の香りが広がります。

この状態の茶葉は、まだ摘みたて同様で、葉の色も緑で、みずみずしくパリッとしています。
これが萎凋作業により、水分が抜けて、どんどんシナシナになっていきます。

今回の体験では、この萎凋が完了した茶葉が参加者に提供されました。
ここから、柔らかく捻りやすいサイズの茶葉を選び取り、茎を取り除いていきます。
ちなみに、この後 揉捻や乾燥といった作業で水分がどんどん抜けていき、生葉 約100gから出来上がる紅茶は、約20g(5分の1くらい)の量になります。

茶葉の選定中に、ウンカ虫(チャノミドリヒメヨコバイ)を発見!!実物初めて見た!ひとりでこっそりテンション上がってしまいました!笑
緑茶を作る場合、このウンカ虫に噛まれた茶葉は色も悪く苦味の強いお茶になってしまうため害虫として扱われるんですが、紅茶作りにおいては、この虫に噛まれた茶葉は蜜のように甘くフルーティーな香りになるという、幸運の虫さんなんです!
このウンカ虫に噛まれた茶樹は、身を守るために防御本能が働き新たな物質を作るのですが、その成分が蜜のような甘い香りの紅茶を生み出してくれます。
キミがいるから紅茶がおいしくなるんだよ~来てくれてありがとう!
揉捻

揉捻とは、葉によじれを与え、揉んでいく作業です。
圧力をかけて揉むことで茶葉に捻りを作っていくとともに、茶汁を出し、空気に触れさせます。
これにより発酵の働きを高め、紅茶にとって大切な発酵を促していきます。
体験では、袋に入れた茶葉をひたすらに力を込めて揉んでいきます。
これが結構体力仕事で大変…!30分くらい続けていきます。

揉み続けること30分程…葉っぱにも撚りが掛かり、水分が出てしっとりしてきました。
この頃には参加者の皆さんも、手揉み作業のしすぎでヘトヘト…!
こうして苦労しながらの揉み作業の体験もイベントの醍醐味ですが、大量に生産するのに全て手作業で作るのはかなり体力も根気もいる作業です。
jpeg-edited-scaled.jpg)
そこで、製茶工場などで大量に効率良く茶葉を揉捻する場合は「揉捻機」という機械が使用されます。
これも実物を見るのは初めてで感動しました!(これはぜひ動画で動いているところを見てほしい!)

揉捻機を使用すると、短時間で大量に、捻りが均一な茶葉が出来上がります。
揉捻した紅茶は茶汁が出てきて、雨上がりの草原を踏み締めたときのような、青々とした大地のような香りが漂ってきていました。
発酵

揉捻後、1時間ほど放置して発酵を進ませます。(その間にお昼休憩)
すると、緑だった茶葉も全体的に色も赤茶っぽく変色してきて、私たちのよく知る紅茶の色形に近付いてきました。
香りを嗅いでみると、初めは青草のような香りだったのが、リンゴのような甘い香りに変化してきました。
実際に変化を目や鼻で感じ取りながら、だんだん紅茶らしくなってきているのを実感できるのには感動!
これはイベントに参加しないと味わえない体験です。

本来は徐々に茶葉を発酵させつつ、次の工程である「乾燥」に移行するのですが、製茶体験イベントでは時間が限られているため、今回は乾燥時間短縮のため特別に「殺青機(さっせいき)」という機械にかけて、あらかじめ ある程度乾燥させます。
本来 殺青機は、不発酵茶の緑茶や、半発酵茶の烏龍茶を作る際に、強制的に発酵を止めるために使用することが多く、完全発酵させる紅茶作りではあまり行わない工程なんだとか。

写真ではわかりづらいですが、この機械の中で、熱風を浴びながらドラム式洗濯機のように茶葉がぐるぐると回っています。
この機械の近くにいる間ずっと、熱風と共にべっ甲のような甘い香りが漂ってきていて、なんとも幸せな気分でした♡
乾燥

パン屋さんにある大きなオーブンのようなこの機械は、乾燥機です。
100℃前後の熱風で、茶葉の水分が3~4%になるまで乾燥させて、茶葉の発酵を止めます。
こうすることで、葉がパリパリの状態になり、褐色になります。
ここまでくると、もう私たちが普段目にしている紅茶の茶葉ですね!

この状態の茶葉のことを「荒茶(あらちゃ)」といいます。
さらにここから混入物を取り除き、等級(茶葉の大きさ)ごとに仕分けて出来上がったものを「仕上げ茶」と呼びます。
完成!みんなで荒茶の飲み比べ!


最後に、出来上がった荒茶を参加者みんなで飲み比べてみました!
一目でわかるくらい、茶葉の様子や、水色が違うのが面白いですね。まさに十人十色!

同じ種類の茶葉を一斉に手揉みしたのに、選んだ茶葉の大きさや手揉みの際の力加減、費やした時間で、こんなにも違うものが出来上がるなんて、紅茶作りって奥が深いです!
「和紅茶で茶産業を盛り上げる」三井農林 開発者担当者にインタビュー!
今回は、nittoh.1909で数々の商品を生み出してきた三井農林の開発者担当者の方に、nittoh.1909について、そして和紅茶について、気になることを直撃取材!熱い思いを語っていただきました!
外国産の紅茶がこれだけ国内外で流通する中で、なぜ今、nittoh.1909では和紅茶に力を入れているのでしょうか?

弊社(三井農林株式会社)は、1909年(明治42年)に設立した「三井合名会社」の山林課(のちの農林課)を起源としています。1927年には初の国産ブランド「三井紅茶」(後の日東紅茶)を販売するなど、およそ100年に渡り日本の紅茶文化と共に歩んできました。
現在、日本における茶全体の生産量が落ち込む中、和紅茶の生産に限っては生産量が増えています。そういった背景もあり、弊社も和紅茶を通してあらためて茶産業を盛り上げたいと考えています。
和紅茶はつくり手によって味や香りに特徴が出やすいため、いま、ここでしか出会えない商品・体験というブランドコンセプトに合致しています。
nittoh.1909は「つなぐ・かなえる・満たされる」場として、みなさまとその時の気持ちに美味しいお茶を共有し、心の贅沢を感じられるブランドとして成長していきたいと思っています。
 Mii(みぃ)
Mii(みぃ)「つくり手によって味や香りに特徴が出やすい」というのは私も実感しています。同じ茶葉でも、作った地域や茶園によってかなり違いが出て面白いですよね!
nittoh.1909はそういった商品で茶産業を盛り上げ、紅茶で心の贅沢を感じられるようなブランドを目指しているんですね!
和紅茶の開発に至った経緯を教えてください


国産の烏龍茶を作ったことが、和紅茶を作る出発点になります。
もともと私自身は、中国茶の原料調達と開発を担当しておりました。
業務をする中で様々な香味バリエーションを持った烏龍茶と出会うことで、中国茶の世界にはまっていきました。
この面白さを日本のお客様へお伝えしたいという想いがあったのですが、その思いとは逆に、当時の烏龍茶はダウントレンドになりつつありました。
そこで国産烏龍茶を作るというきっかけが生まれます。
自らの手で製茶するようになり、香味作りにおける製茶の重要性と可能性を体感し、烏龍茶だけでなく紅茶も作るようになりました。



最初は烏龍茶のご担当だったんですね!
烏龍茶と紅茶って、半発酵茶と発酵茶で、似通ったところもありますし、
そういったところが、紅茶作りにも生きてきているんですね。
商品開発の際、どんなことを心がけて商品を作っていますか?


お客様の立場に立って、「自分だったらこういう商品があったら買うだろう」という仮説に基づき試作します。試作品の評価は自分だけでなく、複数の評価を取り入れるようにしています。
その他に、市場で販売されている商品とは類似しないように心がけています。



nittoh.1909の商品は、本当にどれも今までにない商品ですよね!
特に「Botanytea(ボタニティー)」は「こんなおいしい和紅茶フレーバーティーがこの世にあったの!?」って感動しちゃいました!あれは他では絶対に生み出せない商品ですね。
和紅茶への開発にこれだけ熱量を注げる、その原動力は何ですか?


お茶を作る面白さだと思います。作る現場に触れれば触れるだけ、新しい発見があります。
また、そこから生まれた商品に対して「美味しい」と言って頂けるお客様の言葉も、原動力の一つです。
今後、どんな製品をつくっていきたいですか?


商品開発のサイクルが短い(商品寿命が短い)昨今ですので、長く愛される、且つ「これって三井農林の作る味だよね」と認知されるような商品を創作していきたいと思います。



これからも素敵な商品を楽しみにしております!
最後に、日東紅茶、nittoh.1909のファンの方に一言お願いいたします!


皆様の想いを叶えるべく、当社には個性豊かな開発者がおります。また、nittoh.1909 では「作り手の個性を味わう」をコンセプトにした商品を多数発売しています。彼らから生み出される独創的な商品に今後も期待してください!
いつも飲んでいる紅茶にも、作り手の努力や思いが隠されていて、その熱い思いがギュッと詰め込まれた商品が、私たちの手元に届いてるんだと思うと、より一層、美味しく感じられますよね。
皆さんも、ぜひ紅茶を飲む際は、「この紅茶はどうやって作られたのかな」「どこで、どんな人が、どんなふうにつくったのかな」と想像しながら、そして興味があればぜひ、商品について調べてみたり、今回のような体験イベントに参加したりして、より紅茶を楽しんでみてください。
きっと、日々のティータイムもより豊かに充実するはずですよ♪
Miiオススメのnittoh.1909 商品紹介
Botanytea(ボタニティー)


Miiイチオシ!茶葉も果実も国産の、和紅茶アールグレイです!
香料は一切使用せず、「フレッシュアロマ製法(特許出願中)」という、茶葉に香りを吸わせて着香する特別な技法で作られたアールグレイは、もぎたて果実の香りと茶葉本来の香りがしっかり感じられます。
外国産茶葉のアールグレイしか飲んだことない方は感動するはず!ぜひ一度試していただきたい逸品です。
詳細なレビューは以下の記事をご覧ください。
>> Botanytea-国産ベルガモット-<ドリップバッグ5袋入り> 購入はこちら
>> Botanytea-国産ベルガモット-<リーフ20g> 購入はこちら


この他にもnittoh.1909には、作り手や茶園の個性が光る商品が多数掲載されています。
いつものティータイムをちょっぴり贅沢に、そして、和紅茶をはじめ世界の紅茶をより身近に感じられる、そんな商品をぜひ味わってみてくださいね。
体験後記
製茶体験を通して


私自身、「ティーアドバイザー」の資格を持っているので、紅茶の製茶については知識として知ってはいたのですが、実際に紅茶作りの現場を見たり、茶園・企業といった作り手の方のお話を聞いたりと、このイベントを通して貴重な体験をさせていただきました。
実際に見て、聞いて、触れたことで、普段飲んでいる紅茶や、それを作っている方々へのありがたみがより感じられたと共に、より和紅茶への情熱と興味が湧き上がってきた、印象的な一日となりました。
和紅茶の未来について


茶産業に限ったことではないですが、昨今は円安の影響もあり、外国産の紅茶が高騰しています。
でも、そういった中で逆に、海外ではなく国内の紅茶作りに目を向けてみると、こんなにも素敵な紅茶が身近にあるんだと改めて感じられました。
それと同時に、まだ知られていない商品があったり、「和紅茶」という言葉自体がまだ世間には馴染みがないこともあったりと、日本での和紅茶の認知度はまだまだ低いように思います。
私は業界の人でもなんでもない、ただの紅茶愛好家なので、詳しいことは分からないし、出来ることも本当に小さなことだけです。
でも、私にもできることで、和紅茶の世界はまだまだ広げられるはず!
これからはこの美味しい和紅茶を、国内外にどんどん広めていかなきゃ!
そんなふうに感じました。
私にできることはすごく小さなことかもしれないけど、大好きな和紅茶をもっと世に広めて、盛り上げていく、そのお手伝いができたらいいなと、改めて思いました。
そのためには、まずは和紅茶に興味を持ってもらう、知ってもらうことが大切です。
実際に飲んで、ブログやSNSなどのネット上で紹介したり、口コミで広めたりなど、自分で感じた「これ美味しい!」を発信することが、小さな第一歩になるんでないでしょうか。



この記事を読んで和紅茶に興味を持った皆さんも、ぜひ、自分の「これ美味しい!」という気持ちを大切にして、もしそれを誰かに伝えたいと思ったら進んで自ら発信して、一緒に和紅茶界隈を盛り上げていきましょう!
nittoh.1909のイベントに参加してみませんか?
nittoh.1909では他にも、紅茶好きのためのイベントやセミナーが開催されています。
過去には、和紅茶を楽しむセミナーや、ペアリングをテーマにしたアフタヌーンティーイベント、オンライン茶園ツアーなど、紅茶好きなら気になるテーマのイベントが開催されました。
開催情報はnittoh.1909のメールマガジンでお知らせが届くので、紅茶関連のイベントに興味がある、参加してみたいという方はぜひ、nittoh.1909に会員登録して、最新情報をチェックしてみてください!
また、当ブログでは他にも、nittoh.1909を含めいろいろな紅茶をたくさん紹介しているので、紅茶の最新情報が知りたい方は、ぜひ当ブログのブックマーク(お気に入り登録)と、MiiのTwitterやInstagram、YouTubeのフォローをしてください!






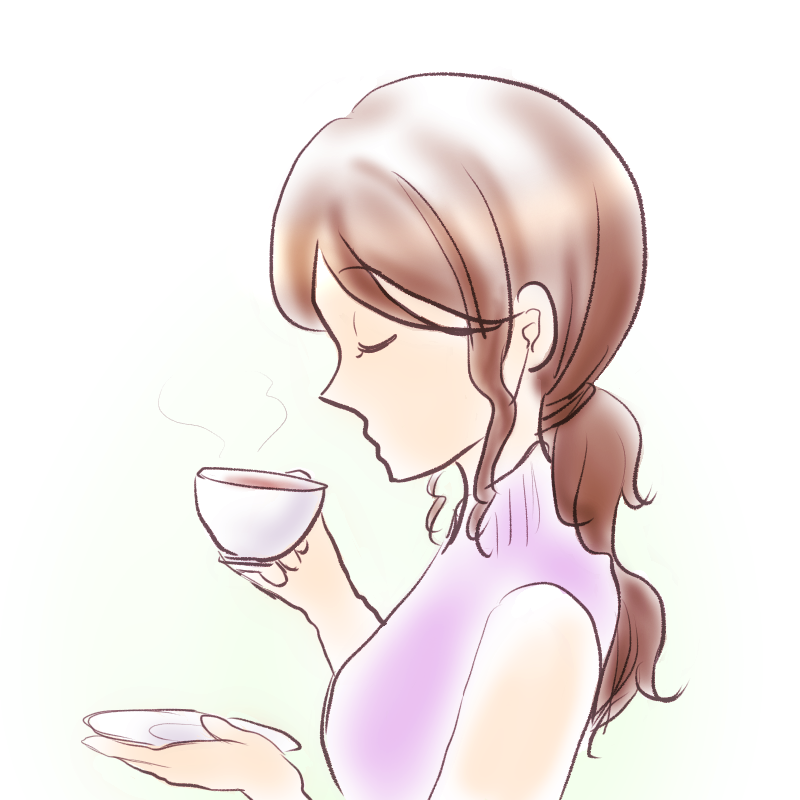








コメント